
|
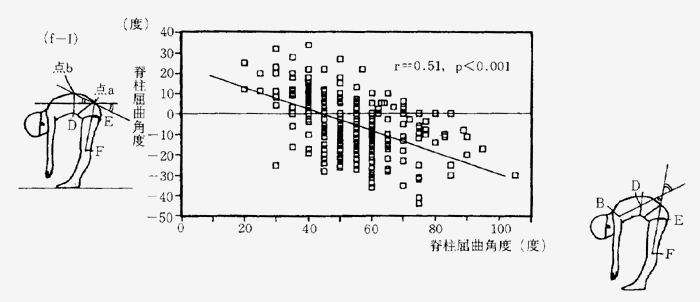
図7 2種の測定法による屈曲角の相関。
ど『角C』の屈曲度は大きくなる傾向がある。また『角E』ではr=-.67をしめす。一方、伸展角度についてみると(図9)、『単一角度e.I』と『多角形法e-?U』の相関は、肋骨下都の『角C」、大転子部の『角E』など尾方(cauda1)のほうが頭方(crania1)より大きい。しかし、『角D」のr=-0。38を最大に、いずれも有意ではあるが高くない。屈曲では『角E』の関与が大きいのにたいし、伸展では体幹各部が関わり、とくに『角D』の関与が大きくなる。以上から、『多角形法』によって、脊柱蛮由度に部位差があること、伸展と屈曲では貢献部位に差があることが推察できる。 2. 脊柱可動域の年齢推移
(1) 屈曲パターンの年齢推移 図10は床からもっとも高くなる基準点を指標に、屈曲パターンの割合をしめしたものである。 5歳を除いて、全年齢で『D型』が多い。40歳以降もとくに低下傾向はないが、floortouchの程度で分類してみると図11のように、加齢退行がみられる。また11・12歳でみぞおち部の高い『C型』(図/2)、5・6歳で『B型』の出現率がまし、この時期のf1oortouch度の低い事例が多くなる。 図13は『多角形法f.II』における『角C』『角D』『角E』の年齢推移をしめしたもの、図14はそれを重ねあわせたものである。図14をみると、どの年齢を通じても、『角C』がもっとも角度が大、つまり屈曲度が低い。また、乳児期と20歳以 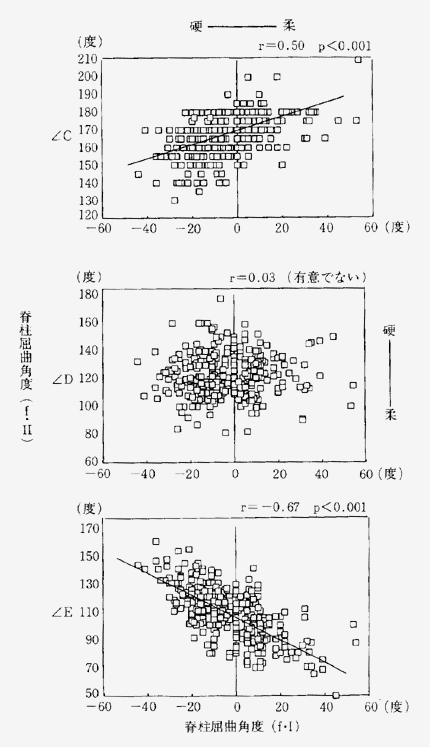
図8 単一角度法と多角形法(∠C、∠D、∠E)による屈曲角の相関。
前ページ 目次へ 次ページ
|

|